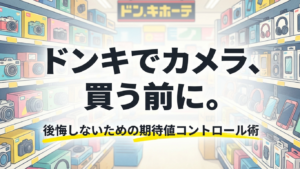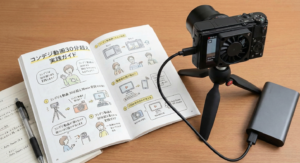SONYのフルサイズミラーレスカメラの歴代モデルについて、どれを選べば良いか迷っていませんか。2013年に市場の常識を覆した初代フルサイズ機「α7」の登場以来、その進化は留まることを知りません。α7Rシリーズの高画素化の進化は風景やスタジオ撮影のレベルを引き上げ、α7Sシリーズの高感度性能と動画特化の設計は映像クリエイターから絶大な支持を受けています。
一方で、α9シリーズのプロ向け高速連写性能は決定的瞬間を捉える力を、そしてα1のフラッグシップモデルとしての特徴は全ての性能を一台に凝縮する究極の形を示しました。これだけ多様なモデルが存在すると、自分の撮影スタイルに最適な一台を見つけるのは難しいものです。この記事では、複雑に見えるラインナップを整理し、歴代モデルのスペック比較一覧や各シリーズの用途別おすすめポイントを解説します。
さらに、ソニーEマウントのレンズ互換性や、新旧モデルの価格とコスパ比較にも触れながら、後悔しないためのフルサイズミラーレスの選び方ガイドとして、あなたのカメラ選びを総合的にサポートします。
- SONYフルサイズミラーレスの進化の歴史と各シリーズの設計思想
- 高画素、高感度、高速連写などモデルごとの強みと得意な撮影分野
- スペックや価格を比較し、自分の目的に合ったモデルを判断する基準
- 豊富なEマウントレンズの中から最適な一本を選ぶためのヒント
SONYのフルサイズミラーレスカメラの歴代モデルの歴史

 |
価格:348679円 |
![]()
- 初代フルサイズ機「α7」の登場
- α7Rシリーズの高画素化の進化
- α7Sシリーズの高感度性能と動画特化
- α9シリーズのプロ向け高速連写性能
- α1のフラッグシップモデルとしての特徴
- 歴代モデルのスペック比較一覧
初代フルサイズ機「α7」の登場

2013年10月に発表されたα7は、カメラの歴史における記念碑的な転換点となりました。それまでフルサイズセンサーを搭載したカメラは、大きくて重いデジタル一眼レフが主流でした。しかし、ソニーはミラーレス構造を採用することで、その常識を覆したのです。
このカメラが画期的だった理由は、小型で軽量なボディに35mmフルサイズセンサーを搭載したことにあります。これにより、プロやハイアマチュアが求める高画質を、圧倒的な機動性と共に手に入れることが可能になりました。ソニーがAPS-CセンサーのNEXシリーズで先行開発していたEマウントを採用したことも、戦略的に非常に巧みでした。新しいマウントをゼロから開発するのではなく、既存のマウント資産を活かすことで、開発速度を上げつつ、コンパクトな設計思想を維持できたのです。
もちろん、初代モデルには弱点も存在しました。当時の評価を見ると、オートフォーカス(AF)の速度や動体追従性能、そして発売当初に利用できるネイティブレンズの種類が少ない点が指摘されています。ただ、これらの課題は、ソニーが市場の反応を見ながら着実に改良を重ねていくための出発点であったと考えられます。初代α7の登場は、単に新製品が一つ増えたというだけでなく、カメラ業界全体の未来をミラーレスへと大きく舵を切らせる、極めて重要な出来事だったのです。
α7Rシリーズの高画素化の進化

α7Rシリーズは、ソニーのフルサイズミラーレスの中で「Resolution(解像度)」を徹底的に追求する系統です。このシリーズの使命は、風景写真家や建築写真家、スタジオで緻密な作品を撮る商業フォトグラファーなど、細部のディテールを極限まで求めるユーザーの要求に応えることにあります。
その進化の歴史は、まさに高画素化の歴史そのものです。2013年に初代α7と同時に発表されたα7Rは、3640万画素という当時としては非常に高い解像度を誇り、ディテールを最大限に引き出すために光学ローパスフィルターを搭載しない設計が採用されました。このコンセプトは後継機にも引き継がれ、2015年のα7R IIでは世界初となる4240万画素の裏面照射型CMOSセンサーを搭載し、高解像度と高感度性能の両立を実現します。
そして、2019年に発売されたα7R IVは、フルサイズミラーレスとして世界で初めて6100万画素の壁を突破し、業界に衝撃を与えました。この圧倒的な画素数は、大判プリントへの対応力はもちろん、大胆なトリミングをしても画質が劣化しにくいという大きな利点をもたらします。最新モデルのα7R Vでは、この6100万画素センサーを継承しつつ、専用のAIプロセッシングユニットを搭載。被写体認識AFの精度を飛躍的に向上させ、高解像度でありながら動く被写体にも強力に対応できるようになりました。
ただし、高画素には注意点も伴います。ファイルサイズが非常に大きくなるため、高性能なパソコンや大容量のストレージが必要になる点は考慮すべきでしょう。また、わずかな手ブレも目立ちやすくなるため、三脚の使用やしっかりとしたホールディングが求められます。
α7Sシリーズの高感度性能と動画特化

α7Sシリーズは、「Sensitivity(感度)」をその名の由来とし、特に暗所での撮影性能とプロフェッショナルな動画機能に特化したラインナップです。このシリーズは、他のモデルとは一線を画すユニークな設計思想を持っています。それは、画素数をあえて低く抑えるという選択です。
初代α7Sが2014年に登場した際、その有効画素数は1220万画素でした。これは当時の他のフルサイズ機と比較してかなり低い数値ですが、これには明確な狙いがあります。画素数を少なくすることで、一つの画素が光を受け取る面積(ピッチ)が広くなり、より多くの光を取り込めるようになります。この結果、ノイズの少ないクリアな画像を、光が乏しい極端な暗所でも撮影できるのです。常用ISO感度は102400、拡張では409600という驚異的な数値を実現しました。
この高感度性能は、動画撮影においても絶大な威力を発揮します。α7Sは、フルサイズセンサーの全画素情報を読み出して4K映像を外部出力できる機能をいち早く搭載。続くα7S IIでは4K動画の内部記録に対応し、さらにα7S IIIでは4K120pという滑らかなスローモーション映像や、階調豊かな10bit 4:2:2での記録が可能になるなど、映像クリエイターの要求に応える形で進化を続けてきました。
このシリーズを選ぶ上での注意点は、静止画の解像度が低いことです。そのため、大きなサイズでのプリントや、撮影後の大幅なトリミングには向きません。あくまで、高感度性能と動画品質を最優先するフォトグラファーやビデオグラファーのための、専門的なツールと位置づけられています。
α9シリーズのプロ向け高速連写性能

α9シリーズは、プロフェッショナルのスポーツ写真や報道の現場で求められる「速度」と「信頼性」を具現化した、ソニーのスピードマスターです。このシリーズの登場は、それまでデジタル一眼レフの独壇場とされてきた高速撮影の領域に、ミラーレスカメラが本格的に参入する狼煙となりました。
2017年に発表された初代α9の最大の革新は、世界で初めて搭載された積層型フルサイズCMOSセンサー「Exmor RS」です。このセンサーは、画素領域と回路領域を別々の層に重ねる構造になっており、信号処理速度が飛躍的に向上しました。これにより、AF/AE追従で最高20コマ/秒という圧倒的な連続撮影を、ファインダー像が途切れない「ブラックアウトフリー」で実現したのです。動きが予測不能なアスリートの一瞬の表情や、野生動物のダイナミックな動きを、かつてない精度で捉え続けることが可能になりました。
さらに、この高速読み出し性能は、電子シャッターの弱点であった「ローリングシャッター歪み(動体歪み)」を劇的に抑制することにも貢献しました。後継機であるα9 IIでは、接続性や操作性をプロのワークフローに合わせてさらに改善。そして2024年に登場したα9 IIIは、世界で初めてグローバルシャッター方式のフルサイズセンサーを搭載するという、再び業界を震撼させる技術革新を成し遂げました。これにより、動体歪みは完全に解消され、全てのシャッタースピードでストロボ同調が可能になるなど、撮影の可能性を大きく広げています。
α9シリーズは、一瞬を逃せないプロフェッショナルのためのカメラであり、その性能に見合う高価な価格設定です。一般的な撮影用途ではオーバースペックとなる可能性もありますが、速度こそが正義となる撮影分野においては、他の追随を許さない絶対的な存在と言えるでしょう。
α1のフラッグシップモデルとしての特徴

2021年に登場したα1は、ソニーがそれまで培ってきた技術のすべてを結集させた、究極のフラッグシップモデルです。このカメラは、特定の性能に特化するのではなく、高解像度、高速性能、そして高度な動画機能という、プロが求める全ての要素を一台に凝縮するという野心的なコンセプトのもとに開発されました。
α1の心臓部には、新開発の有効約5010万画素の積層型CMOSセンサーが搭載されています。これにより、α7Rシリーズに迫る高精細な描写力を持ちながら、α9シリーズを上回る最高30コマ/秒のブラックアウトフリー高速連写を実現しています。さらに、動画性能においても、α7Sシリーズが得意としてきた領域をカバーし、8K30pという次世代の映像制作にも対応可能です。
言ってしまえば、α1はα7Rシリーズの「解像度」、α9シリーズの「速度」、そしてα7Sシリーズの「動画」という、各シリーズの長所を併せ持つ「全部入り」のカメラなのです。これにより、フォトグラファーは撮影シーンに応じてカメラを持ち替える必要がなくなり、一台であらゆるジャンルのプロフェッショナルな仕事に対応できます。
もちろん、この妥協のない性能は、価格にも反映されています。α1はソニーのミラーレスカメラの中でも最も高価なモデルの一つであり、その性能を完全に引き出すためには、最高級のG Masterレンズ群との組み合わせが推奨されます。あらゆる状況で最高のパフォーマンスを求める、トッププロフェッショナルやプロダクションのための究極の一台と言えるでしょう。
歴代モデルのスペック比較一覧
SONYのフルサイズミラーレスカメラは、多岐にわたるシリーズとモデルが存在し、その進化の過程を把握するのは容易ではありません。ここでは、各シリーズの主要な歴代モデルの基本的なスペックを一覧表にまとめました。これにより、各モデルがどの世代に位置し、どのような特徴を持っているのかを客観的に比較できます。
以下の表は、カメラ選びの参考として、解像度や連写性能、動画機能といった主要な性能の違いが一目で分かるように整理したものです。
| シリーズ | モデル名 | 発売時期 | 有効画素数 | 最大連写速度 (AF/AE追従) | 主な動画性能 |
| α7 | α7 III | 2018年3月 | 約2420万 | 約10コマ/秒 | 4K 30p |
| α7 IV | 2021年12月 | 約3300万 | 約10コマ/秒 | 4K 60p | |
| α7R | α7R III | 2017年10月 | 約4240万 | 約10コマ/秒 | 4K 30p |
| α7R IV | 2019年9月 | 約6100万 | 約10コマ/秒 | 4K 30p | |
| α7R V | 2022年11月 | 約6100万 | 約10コマ/秒 | 8K 24p | |
| α7S | α7S II | 2015年9月 | 約1220万 | 約5コマ/秒 | 4K 30p (内部) |
| α7S III | 2020年10月 | 約1210万 | 約10コマ/秒 | 4K 120p | |
| α9 | α9 | 2017年5月 | 約2420万 | 約20コマ/秒 | 4K 30p |
| α9 II | 2019年11月 | 約2420万 | 約20コマ/秒 | 4K 30p | |
| α9 III | 2024年1月 | 約2460万 | 約120コマ/秒 | 4K 120p | |
| α1 | α1 | 2021年3月 | 約5010万 | 約30コマ/秒 | 8K 30p |
| α1Ⅱ | 2024年12月 | 約5010万 | 約30コマ/秒 | 8K 30p | |
| α7C | α7C | 2020年10月 | 約2420万 | 約10コマ/秒 | 4K 30p |
| α7C II | 2023年10月 | 約3300万 | 約10コマ/秒 | 4K 60p |
この表を見ると、世代が新しくなるにつれて、解像度、連写速度、動画性能が着実に向上していることが分かります。一方で、α7Sシリーズのように、特定の性能を追求するために画素数を抑えているモデルもあり、各シリーズのコンセプトの違いが明確に現れています。


自分に合うSONYのフルサイズミラーレスカメラの歴代モデル

- 各シリーズの用途別おすすめポイント
- 新旧モデルの価格とコスパ比較
- ソニーEマウントのレンズ互換性
- フルサイズミラーレスの選び方ガイド
- あなたに合うSONY ミラーレス 歴代 フルサイズは
各シリーズの用途別おすすめポイント
SONYのフルサイズミラーレスは、各シリーズに明確なコンセプトとターゲットユーザーが設定されています。自分の撮影スタイルや主な被写体を考えることが、最適な一台を見つけるための第一歩です。
α7シリーズ:万能なスタンダードモデル
α7シリーズは、高画質、高速AF、動画機能といった要素を高いレベルでバランス良く搭載した「究極のスタンダード」です。風景、ポートレート、スナップ、イベント撮影、そして本格的な動画制作まで、幅広いジャンルを一台でこなしたいと考える方におすすめします。特にα7 IVは「新ベーシック」と称され、静止画と動画の両方を高い次元で楽しみたいハイブリッドシューターにとって最適な選択肢の一つです。
α7Rシリーズ:解像度を求めるなら
前述の通り、α7Rシリーズは解像力を最優先する方向けです。壮大な風景を隅々までシャープに写し撮りたい、あるいは広告やファッションの分野で大判プリントや大胆なトリミングが求められるプロフェッショナルに最適です。作品の細部にまでこだわり、圧倒的なディテールを追求するなら、このシリーズがその要求に応えてくれます。
α7Sシリーズ:暗所撮影と映像制作のプロへ
α7Sシリーズは、光の少ない環境での撮影や、映画のようなクオリティの映像作品を制作したいビデオグラファーのための専門機材です。夜景や星空の撮影、ライブハウスでの記録、ドキュメンタリー映画の制作など、高感度性能が結果を左右する場面で真価を発揮します。
α7Cシリーズ:携帯性を重視するあなたに
α7Cシリーズの「C」は「Compact(コンパクト)」を意味します。フルサイズセンサーの画質を、APS-C機並みの小型・軽量ボディに凝縮したのが最大の特徴です。旅行や登山、日常的なスナップなど、機材の重さを気にせず気軽に持ち出して高画質な写真を撮りたい方にぴったりです。
α9シリーズとα1:プロフェッショナルのための選択肢
α9シリーズはスポーツや報道、野生動物など、一瞬を逃せない撮影に特化した「速度」のプロフェッショナルモデルです。一方、α1は解像度、速度、動画の全てを最高レベルで兼ね備えた究極のフラッグシップ機となります。これらのモデルは、その性能を最大限に必要とするトッププロ向けの選択肢と言えるでしょう。
新旧モデルの価格とコスパ比較

カメラ選びにおいて、予算は非常に重要な要素です。最新モデルは常に最高の性能を持っていますが、必ずしもそれが唯一の正解ではありません。一つ前の世代、いわゆる「型落ち」モデルも、コストパフォーマンスを考えると非常に魅力的な選択肢となります。
例えば、現行のスタンダードモデルであるα7 IVは非常に高性能ですが、その一つ前のα7 IIIも、今なお多くのプロに愛用されるほど完成度の高いカメラです。発売から時間が経過しているため、新品・中古ともに価格がこなれてきており、α7 IVとの価格差をレンズ購入の予算に充てる、という賢い選択も可能になります。
このように、新旧モデルを比較する際は、単にスペックの優劣だけでなく、価格差と性能差のバランスを考えることが大切です。最新機能が本当に自分の撮影に必要かどうかを冷静に見極めましょう。特に、AF性能や動画機能の進化は著しいですが、風景撮影がメインでじっくり被写体と向き合うスタイルの方であれば、旧モデルでも全く不足を感じないケースは少なくありません。
中古市場も積極的に活用することをおすすめします。信頼できるカメラ専門店であれば、状態の良い中古品を適正な価格で購入でき、予算を大幅に抑えることが可能です。新旧モデルの価格と性能を天秤にかけ、自分にとって最もコストパフォーマンスの高い組み合わせを見つけることが、後悔しないカメラ選びの鍵となります。
ソニーEマウントのレンズ互換性
カメラボディの性能を最大限に引き出すためには、レンズの選択が極めて重要です。ソニーのフルサイズミラーレスが多くのユーザーから支持される大きな理由の一つに、Eマウントシステムの「レンズの豊富さ」が挙げられます。
純正レンズのラインナップ
ソニーの純正レンズは、いくつかのグレードに分かれています。
- G Master (GM):
解像度と美しいボケ味を最高レベルで両立させた、ソニー最高峰のレンズシリーズです。プロフェッショナルの厳しい要求に応えるための、妥協のない設計がなされています。 - Gレンズ:
G Masterに次ぐ高性能レンズ群で、優れた描写性能と操作性を誇ります。比較的手に入れやすい価格のモデルも多く、ハイアマチュアに人気です。 - ZEISS(ツァイス)レンズ:
ドイツの名門光学メーカー、カール・ツァイスとの共同開発によるレンズです。シャープでコントラストの高い、独特の描写が魅力です。
サードパーティ製レンズの魅力
Eマウントの大きな強みは、ソニー純正以外のメーカー(サードパーティ)からも、非常に多くの魅力的なレンズが発売されていることです。シグマ(SIGMA)やタムロン(TAMRON)といったメーカーは、純正レンズに匹敵する、あるいはそれを超えるような描写性能を持つレンズを、より手頃な価格で提供しています。これにより、ユーザーは非常に幅広い選択肢の中から、自分の予算や表現スタイルに合ったレンズを選ぶことが可能です。
注意点:APS-C用レンズについて
Eマウントは、フルサイズ用と、より小型なAPS-Cセンサー用のレンズが共通のマウントになっています。フルサイズ機にAPS-C用のレンズを装着することも可能ですが、その場合は画角が約1.5倍にクロップ(切り取られ)され、カメラが持つ本来の画素数を活かせなくなる点には注意が必要です。購入時には、レンズがフルサイズに対応しているか(「FE」という表記が目印)を必ず確認しましょう。
フルサイズミラーレスの選び方ガイド

これまで各シリーズの特徴やレンズについて解説してきましたが、最終的に自分に合う一台を選ぶための具体的なステップをまとめます。以下の3つの軸で自分のニーズを整理することで、数多くの選択肢の中から最適なカメラが自然と見えてきます。
ステップ1:予算の上限を決める
まず最初に、カメラシステム全体(ボディ+レンズ)にかけられる予算を明確にしましょう。カメラはボディだけでは撮影できません。特にフルサイズの場合、高性能なレンズはボディ本体と同じか、それ以上に高価なことも珍しくありません。最初にレンズ1本を含めた総額の予算を決めることで、選択肢を現実的な範囲に絞り込むことができます。型落ちモデルや中古品を視野に入れることで、同じ予算でもより高性能なシステムを組める可能性があります。
ステップ2:主な被写体と撮影スタイルを考える
次に、あなたが何を一番撮りたいのかを考えます。
- 風景や星空: α7Rシリーズのような高解像度モデルや、α7Sシリーズのような高感度モデルが力を発揮します。
- ポートレート: どのモデルでも高品質な写真が撮れますが、瞳AFの性能が高い新しい世代のカメラが有利です。
- スポーツや動物: α9シリーズやα1のような高速連写性能を持つモデルが最適です。
- 旅行や日常スナップ: α7Cシリーズのようなコンパクトなモデルが持ち運びに便利です。
- 動画制作: α7Sシリーズや、4K60p以上に対応するα7 IV以降のモデルがおすすめです。
このように、主な被写体を明確にすることで、どのシリーズが自分に向いているかが見えてきます。
ステップ3:求める携帯性と操作性を考慮する
最後に、カメラをどのように使いたいかを考えます。毎日カバンに入れて持ち歩きたいのか、それとも三脚に据えてじっくり撮影することが多いのか。α7Cシリーズのような小型軽量モデルと、α1のような堅牢で大型のモデルとでは、使い勝手が大きく異なります。可能であれば、実際にカメラ専門店などで実機を手に持ち、グリップの握りやすさやボタンの配置、重さなどを体感してみることを強くおすすめします。自分の手にしっくりと馴染むかどうかも、長く愛用するための大切な要素です。
あなたに合うSONYのフルサイズミラーレスカメラの歴代モデル
この記事では、SONYのフルサイズミラーレスカメラの歴代モデルについて、その進化の歴史から各シリーズの特徴、そして自分に合った一台を見つけるための選び方までを詳しく解説しました。最後に、記事全体の重要なポイントを箇条書きでまとめます。
- SONYは2013年の初代α7でフルサイズミラーレス市場を開拓した
- α7シリーズは性能バランスに優れた万能なスタンダードモデル
- α7Rシリーズは風景やスタジオ撮影向けの解像度特化ライン
- α7Sシリーズは画素数を抑え高感度と動画性能を追求した専門機
- α7Cシリーズはフルサイズ画質を小型軽量ボディで実現
- α9シリーズは積層型センサーでプロの高速撮影ニーズに応える
- α1は解像度・速度・動画を兼ね備えた究極のフラッグシップ機
- 積層型センサーやAI処理ユニットが近年の技術革新を牽引
- グローバルシャッター搭載のα9 IIIは動体歪みを完全になくした
- Eマウントは純正・サードパーティ共にレンズの選択肢が非常に豊富
- 型落ちモデルはコストパフォーマンスに優れた賢い選択肢となり得る
- カメラ選びはボディとレンズを合わせた総予算で考えることが大切
- 主な被写体を明確にすることが最適なシリーズを見つける近道
- 携帯性や操作性は実際に店舗で実機に触れて確認するのが理想
- あなたの撮影スタイルに優先順位をつけることが後悔しない選び方の鍵