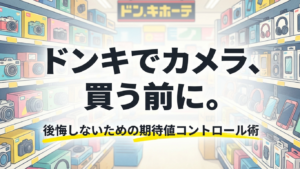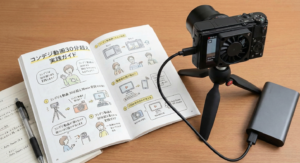ニコンのZマウントシステムにおいて、待望のZ5IIと最新鋭のZ6IIIは、多くの写真愛好家が注目する2つのモデルです。これからフルサイズミラーレスの世界に飛び込む方や、旧機種からのステップアップを考えている方にとって、このNikon Z5II vs Z6IIIの比較は、失敗や後悔のない選択をするための重要な判断材料となります。
この記事では、単なるスペックの羅列に留まらず、センサー性能と画質の違いから、オートフォーカス精度と追従性能比較、そして連写速度とシャッターフィーリングに至るまで、両機の核心に迫ります。また、動画撮影機能と映像品質、ファインダー・背面モニターの進化、ボディデザインと操作性の違いといった実用面での差も詳しく解説します。
さらに、バッテリー持ちと長時間撮影性能や、最も気になる価格帯とコストパフォーマンスを分析し、最終的にどんなユーザーにおすすめかを明らかにしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたの撮影スタイルや予算に本当に合った一台がどちらなのか、明確な答えが見つかっているはずです。
- 両モデルのスペックと性能の具体的な違い
- それぞれのカメラが得意とする撮影シーン
- 価格と性能から見たコストパフォーマンス
- あなたの撮影スタイルに合うモデルの選び方
Nikon Z5II vs Z6IIIの比較:核心性能の徹底分析
- センサー性能と画質の違いを解説
- オートフォーカス精度と追従性能比較
- 連写速度とシャッターフィーリングは?
- 動画撮影機能と映像品質の差
- ファインダー・背面モニターの進化
センサー性能と画質の違いを解説

両モデルの画質を決定づける心臓部、イメージセンサーには根本的な思想の違いが見られます。Z6IIIは世界初の「部分積層型CMOSセンサー」を搭載しており、これが圧倒的な高速性能を実現する源泉となっています。一方、Z5IIは定評のある裏面照射型(BSI)CMOSセンサーを採用し、こちらは堅実な高画質を提供します。
Z6III:スピードを追求した部分積層型センサー
Z6IIIのセンサーは、読み出し速度をZ6IIの約3.5倍にまで高めた革新的な技術です。この高速化により、電子シャッター使用時のローリングシャッター歪みが大幅に抑制され、動きの速い被写体でも自然な描写が可能になりました。
ただ、この高速性能にはトレードオフも存在します。ベースISO感度におけるダイナミックレンジは、Z6IIなどの従来機に比べてわずかに狭くなる傾向があります。これは、風景撮影などで暗部を大幅に持ち上げるような現像を行う際、RAWデータに若干の余裕のなさを感じる可能性があることを意味します。
Z5II:高画質とコストを両立するBSIセンサー
Z5IIに搭載が噂されるのは、Z6やZfで実績のある2450万画素クラスのBSIセンサーです。初代Z5の表面照射型センサーから大きく進化し、特に暗い場所での撮影におけるノイズ耐性や色再現性の向上が期待できます。
興味深いことに、Z5IIはベースISO感度でのダイナミックレンジにおいて、Z6IIIを上回る可能性があります。つまり、価格が下のモデルでありながら、特定の画質指標では上位モデルを凌駕するという逆転現象が起こり得るのです。高感度性能については、両機ともに画像処理エンジン「EXPEED 7」の恩恵を受け、常用ISO64000まで実用的な画質を維持すると考えられます。
| スペック項目 | Nikon Z6 III | Nikon Z5 II |
| センサータイプ | 世界初 部分積層型CMOSセンサー | 裏面照射型(BSI) CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 2450万画素 | 約2450万画素 |
| 画像処理エンジン | EXPEED 7 | EXPEED 7 |
| 常用ISO感度 | 100-64000 | 100-64000 |
| ダイナミックレンジ | 高速性能を優先 | 高感度に優れる |
オートフォーカス精度と追従性能比較

オートフォーカス性能は、Z6IIIとZ5IIで最も大きな飛躍を遂げる分野の一つです。両機ともにフラッグシップ機譲りの画像処理エンジン「EXPEED 7」を搭載するため、AFの基本性能は非常に高いレベルで共通化されました。
Z6IIIのAFシステムは、Z9やZ8からアルゴリズムを継承しており、まさにフラッグシップ級の性能を誇ります。ディープラーニング技術を活用した被写体検出機能は、人物、犬、猫、鳥、飛行機、列車、車、バイクといった9種類の被写体を高精度に認識し、一度捉えた被写体を粘り強く追従します。-10EVという極めて暗いシーンでも合焦可能な低照度AF性能も、撮影シーンを選ばない信頼性を担保しています。
一方、Z5IIのAF性能向上も目覚ましいものに。初代Z5の弱点であった動体追従や低照度AFが、「EXPEED 7」の搭載によって劇的に改善されました。Z6IIIと同じ被写体検出アルゴリズムが実装される可能性が高く、これまでZ5では難しかった動きのあるポートレートや、カジュアルなスポーツ撮影でも、安心してシャッターを切れるようになりました。
ただし、両者の間には明確な性能差が存在します。Z6IIIの「部分積層型センサー」がもたらす高速なセンサー読み出しは、AFの演算速度や追従のスムーズさに直結します。このため、特に予測不能な動きをする被写体に対する追従の安定性や、高速連写中のAF追従精度においては、Z6IIIに軍配が上がると考えられます。
連写速度とシャッターフィーリングは?
連写性能は、それぞれのカメラがターゲットとするユーザー層を最も明確に示しています。Z6IIIがプロの動体撮影にも応える速度を備える一方、Z5IIはアマチュアが必要とする十分な性能を持つ、バランスの取れた仕様になっています。
Z6IIIは、まさにアクションのスペシャリストです。メカシャッターで約14コマ/秒、電子シャッターでは20コマ/秒(RAW)という高速連写を実現しています。さらに、JPEG撮影に限定すれば、フル解像度で60コマ/秒、APS-Cクロップでは120コマ/秒という異次元の速度に達します。
そして、Z6IIIを象徴する機能が「プリキャプチャー」です。これはシャッターボタンを全押しする最大1秒前から画像を記録できる機能で、鳥が飛び立つ瞬間やゴールシーンなど、決定的な一瞬を逃すリスクをほぼゼロにしてくれます。
これに対して、Z5IIの連写速度は初代Z5の4.5コマ/秒から、約11〜15コマ/秒へと大幅に向上しています。この速度は、風景、ポートレート、スナップといった一般的な撮影ジャンルでは十分すぎる性能であり、運動会での子どもの撮影など、日常的な動体撮影にもしっかりと対応できます。加えてプリキャプチャー機能が搭載されました。
動画撮影機能と映像品質の差

動画性能において、Z6IIIはプロの映像制作用途にも耐えうるハイブリッド機としての地位を確立しています。対照的に、Z5IIは初代Z5の弱点を克服し、コンテンツクリエイターにとって非常に魅力的な選択肢へと進化を遂げました。
Z6IIIの最大の強みは、12bitの6K N-RAWやProRes RAWをカメラ内部で記録できる点にあります。これは通常、高価なシネマカメラでしか実現できない機能であり、カラーグレーディングなどポストプロダクションでの編集に絶大な自由度をもたらします。また、4K 60p映像は6Kからのオーバーサンプリングによって生成されるため、極めて高精細でシャープな映像を得られます。
一方で、Z5IIは動画クリエイターにとって「必要十分」な機能を、高いレベルで実現。初代Z5の大きな弱点だった1.7倍のクロップがなくなり、センサー全幅を活かしたクロップなしの4K 30p撮影が可能に。さらに、10bitの内部記録とN-Logプロファイルの搭載により、Z5の8bit映像とは比較にならない豊かな色情報が得られ、本格的なカラーグレーディングにも対応できるようになりました。
| 解像度/フレームレート | Nikon Z6 III | Nikon Z5 II |
| 内部RAW動画 | 6K 60p (N-RAW) | – |
| 4K UHD (クロップなし) | 6Kオーバーサンプリング (最大60p) | 全画素読み出し (最大30p) |
| 4K UHD (クロップあり) | APS-Cクロップ (最大120p) | APS-Cクロップ (最大60p) |
| Logプロファイル | N-Log | N-Log |
| ビット深度 | 12bit / 10bit / 8bit | 10bit / 8bit |
ファインダー・背面モニターの進化
電子ビューファインダー(EVF)と背面モニターは、撮影体験の質に直結する重要な要素です。この点において、Z6IIIは他の追随を許さない圧倒的なスペックを備えています。
Z6IIIのEVFは、576万ドットという非常に高い解像度に加え、最大輝度4000nit、そしてDCI-P3の広色域カバーという、クラス最高の仕様を誇ります。これにより、非常に明るい屋外でも被写体を隅々までクリアに確認でき、光学ファインダーに迫る自然な見え方を実現しています。連写中の表示もブラックアウトフリーに近く、動体を追い続ける際のストレスがありません。
一方、Z5IIのEVFは、Zfと同等とされる369万ドットのものが搭載されます。これはZ6IIIには及ばないものの、初代Z5からは大幅な進化であり、多くのユーザーにとって十分すぎるほどの精細さと見やすさを提供してくれます。
背面モニターについては、両機ともにバリアングル式が採用。Z6IIIはすでに210万ドットの高精細なバリアングル液晶を搭載しており、縦位置撮影や自撮りなど、アングルの自由度を大きく向上させています。Z5IIも同様の機構を採用することで、初代Z5のチルト式から利便性が飛躍的に高まりました。
Nikon Z5II vs Z6IIIの比較:購入前の最終チェック
- ボディデザインと操作性の違い
- バッテリー持ちと長時間撮影性能
- 価格帯とコストパフォーマンスを考察
- 結局どんなユーザーにおすすめか
- 総括:Nikon Z5II vs Z6III 比較の結論
ボディデザインと操作性の違い

カメラの性能を最大限に引き出すには、手に馴染むボディデザインと直感的な操作性が欠かせません。Z6IIIとZ5IIは、ターゲットユーザーに合わせて、堅牢性や操作系に違いが設けられると考えられます。
Z6IIIのボディは、プロ機であるZ8に匹敵する防塵防滴性能を備えており、-10℃の耐低温性能も確保されています。過酷な環境下での撮影にも安心して臨める高い信頼性が魅力です。ボタン配置もZ8やZ9の思想を受け継ぎ、プロユーザーがスムーズに操作できるよう洗練されています。
対照的に、Z5IIはZ6IIIのデザインをベースにしつつも、コストを抑えるために複合素材をより多く使用する可能性があるとされています。それでも、ニコン機らしい堅牢な作りと、一定レベルの防塵防滴性能は備えてくるはずです。アマチュアユーザーが日常的に使う上で、不安を感じることはないでしょう。
記録メディアの選択も、両者の性格を明確に分けています。Z6IIIは高速なCFexpress (Type B)カードと汎用性の高いSD (UHS-II)カードのデュアルスロットを採用しています。RAW動画や高速連写の性能をフルに活かすには高価なCFexpressカードが必須です。
これに対し、Z5IIはデュアルSD (UHS-II)カードスロットを搭載しています。多くのユーザーが既に所有しているSDカードを流用できるため、導入コストを大幅に抑えられる点が大きなメリットになります。
バッテリー持ちと長時間撮影性能
バッテリー性能は、特に長時間の撮影や旅行先で重要となるポイントです。Z6IIIとZ5IIは、共通の「EN-EL15c」バッテリーを使用しますが、カメラ内部の消費電力によって撮影可能枚数に差が出る可能性があります。
Z6IIIは、高性能なEVFや高速処理を行うプロセッサーを搭載しているため、電力消費はZ6IIよりも増加する傾向にあります。公式サイトによると、ファインダーのみ使用時の撮影可能枚数は約360枚(「モニターモードの優先」を「ファインダーのみ」に設定時)とされています。ただ、省電力モードも用意されており、使い方次第で撮影枚数を延ばすことは可能です。
Z5IIについては、Z6IIIよりも省電力なEVFを搭載していることなどから、一枚のバッテリーでより多くの枚数を撮影できると思われますが、初代Z5がファインダー使用時で約390枚であったことを考えると、同等かそれ以上のスタミナが期待できます。
また、長時間の動画撮影における熱対策も考慮すべき点です。Z6IIIは、内部RAW記録など発熱の大きい撮影モードを長時間サポートするために、効率的な放熱設計が施されています。4K/60pで125分という長時間の連続記録が可能なのは、この設計の賜物です。Z5IIはZ6IIIほど要求の厳しい動画モードは持たないため、熱問題がシビアな懸念事項になる可能性は低いと考えられます。
価格帯とコストパフォーマンスを考察
Z6IIIのニコンダイレクトでの販売価格は、ボディのみで435,600円(税込)となっています。これは、ソニーのα7 IVやキヤノンのEOS R6 Mark IIといった直接の競合機と同等か、やや高めの価格設定です。しかし、その中には内部RAW動画記録やクラス最高のEVF、プリキャプチャーといった、上位機種に匹敵する機能が含まれており、その性能を最大限活用できるユーザーにとっては価格に見合う価値があると言えます。
一方、Z5IIの価格は、20万円台前半から中盤の範囲に収まっています。この価格帯で、EXPEED 7プロセッサーによる高性能AFやクロップなしの4K動画(30P)は、コストパフォーマンスの高いカメラとなります。
Z6IIIの価値は、そのスピード性能やプロ級の動画機能を直接的に仕事や作品づくりに活かせる人にとって最大化されます。逆に言えば、多くの趣味のカメラマンにとって、Z6IIIはオーバースペックになる可能性があります。その価格差で、高性能なZマウントレンズを一本購入できることを考えると、Z5IIはより広範なユーザーにとって「賢い選択」となる可能性も。
結局どんなユーザーにおすすめか

これまでの分析を踏まえると、どちらのカメラを選ぶべきかは、あなたの撮影スタイルと予算によって明確になります。両者は競合するのではなく、異なるニーズに応えるために用意された選択肢です。
Nikon Z6 IIIを選ぶべきユーザー
プロフェッショナルや、スポーツ、野生動物、航空機といった動体撮影に情熱を注ぐハイアマチュアの方に最適です。最高の連写速度とプリキャプチャー機能がもたらす「撮り逃さない」安心感は、何物にも代えがたい価値があります。また、12bit RAW動画を内部記録できるため、本格的な映像制作を行うビデオグラファーにとっても強力なツールとなります。高い初期投資を、決定的な瞬間を捉えるための必要経費として正当化できる方におすすめです。
Nikon Z5 IIを選ぶべきユーザー
デジタル一眼レフからのステップアップを考えている方や、風景、ポートレート、旅行、家族写真などを中心に楽しむ趣味のカメラマンに最適な選択肢となるでしょう。Z6IIIに迫る信頼性の高いAF性能と、十分な高画質を、優れたコストパフォーマンスで手に入れられます。本格的なRAW動画は不要でも、SNSやYouTube向けの高品質な10bit Log動画は撮影したい、という現代的なニーズにも応えてくれます。カメラボディの予算を抑え、その分をレンズに投資したいと考える賢明なユーザーにこそ、価値のある一台と言えます。
総括:Nikon Z5II vs Z6IIIの比較の結論
この記事では、Nikon Z6IIIと噂されるZ5IIについて、性能や特徴を多角的に比較してきました。最後に、両モデルを選択する上での重要なポイントをまとめます。
- Z6IIIは圧倒的なスピードを誇るミニ・フラッグシップ機
- Z5IIは優れたコストパフォーマンスな万能機
- センサーはZ6IIIが部分積層型、Z5IIはBSI型(裏面照射型)
- 画質はダイナミックレンジでZ5IIが有利
- 両機ともEXPEED 7搭載でAF性能は大幅に向上
- 動体追従の安定性はセンサー読み出しの速いZ6IIIが優位
- 連写はZ6IIIがプロ向け、Z5IIは趣味として十分な速度
- Z6IIIは決定的な瞬間を逃さないプリキャプチャー機能を搭載
- 動画はZ6IIIが内部RAW記録対応のプロ仕様
- Z5IIはクロップなし4K30pや10bit Log対応で大幅進化
- EVFは解像度、輝度ともにZ6IIIがクラス最高峰
- 記録メディアはZ6IIIがCFexpress、Z5IIはデュアルSD
- 価格差は大きく、レンズ資産への投資計画も考慮すべき
- スポーツや野鳥撮影ならZ6IIIが最適な選択肢
- 風景やポートレートが中心ならZ5IIが賢い選択